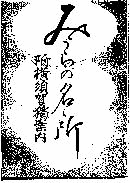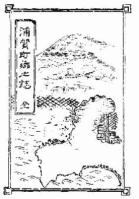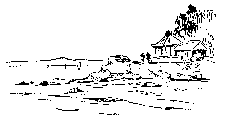浦賀町郷土誌
第四編 鴨居郷土誌
第一章 自然界
第一節 地 界
一、位 置
(1)東南は内海に瀬し西は字浦賀及び字大津に連り北は字走水に接す。
(2)区分ー三軒家、腰越、東、宮原、中台、北方、脇方
二、地 勢
第一編 第五章 第一節を見よ。
(鴨居は、西北に山を負い、東西は海に臨む。立野山は西方にあり、高さ百八十尺あり。
山脈連互して西の方字浦賀を経て字大津に至り、南は鳥ヶ崎に達す。此の間山径樵
路数条あり。堂ヶ谷山は東方にあり。高さ二百尺、三脈は北東に走り、北は字走水に
連り、東は観音崎に至りて海に突入す。山路樵路数条あり。)
三、土 質
第一編 第五章 第七節を見よ。
(一般に色黒く質は黒壌土及び黒塗泥間に小砂礫を雑す。其質中等に位す。小原台は
赤壌土なり。何れも五穀、菽麦、蔬菜の栽培に適す。)
四、広 袤
(1)東西廿三町 南北十六町四十六間 周囲二里五町 面積五十八万三千五百五十六
坪あり。
(2)明和八年の調査によれぱ東西廿八町 南北十八町余とあり。
第二節 水 界
一、 河
第一編 第五章 第三節を見よ。
(和田川=水源を大ヶ谷山間より発して湾流すること六町にして立野山より発する水源と
合して南方宮原に至りて海に入る。巾は二間乃至三間、深さ一尺より四尺内外を有す。
水勢緩にして舟筏を通ぜず。)
二、湖 沼
第一編 第五章 第五節を見よ。
(鴨居の腰越堰=腰越谷戸にあり。東西三十五間、南北二十間、満水の時深さ六尺、
田地三町八反歩の灌漑に供す。)
第三節 気 界
一、気 候
第一編 第六章を見よ。
(一、県燈台に於ける観測をあぐれば次の如し(明治三十七年)
気圧 最低 七四一・〇糎 最高 七七一・〇糎 平均 七五五糎
温度 同 四度 同 三〇度 同 十七・七三度
雨量 最小 九糎 最多 二三三・三糎 同 一二四・二糎
二、風向=冬季は北風多く夏季は南風多し。暴風雨及び烈風は北又は西南風に多し。
三、霜=霜は十一月下旬若くは十二月初旬より初見し、一月中旬より二月の始めに
至りて見ざるに至る。但し如何に降霜の激しかりしことあるも農産物に害をなすに
至らず。
四、雪は至って少量なり。三寸以上の降雪を見るは稀なり。而して一年中降雪は僅
に一、二回にすぎず。
五、気候は健康に適す。
第二章 人 文 界
第一節 戸 口
一、戸 数
(1)明和八年の調査ー弐百七拾五戸
(2)明治十九年一月一日調査ー参百参拾六戸
(3)明治二十一年十二月調生業別戸数ー農業五十五戸、商業四十五戸、
農商兼業三十戸 工業六戸 漁業弐百戸
(4)現時の人口ー約二千三百人
第二節 教 化
一、神 社
| 社名 |
祭神 |
社格 |
境内坪数 |
創立年月 |
祭日 |
八 幡 社
末社二 |
誉 田 別 命 |
村 社 |
四六六 |
慶長元年三月 |
八月十五日
氏子三三六戸 |
| 須賀神社 |
素 盞 鳴 命 |
村 社 |
九〇 |
元禄元年八月 |
七月七日
氏子 同 |
| 神 明 社 |
天 照 大 神 |
無格社 |
二四 |
永正二年五月 |
十月二十一日 |
| 亀 崎 社 |
咲屋此売命 |
無格社 |
六 |
元禄元年正月 |
七月十四日 |
| 稲荷神社 |
食 保 神 |
無格社 |
一三 |
元和三年二月 |
二月十日 |
| 五霊神社 |
鎌倉権五郎景政 |
無格社 |
一五 |
未詳 |
四月十三日 |
| 近戸神社 |
|
無格社 |
|
|
|
| 山 神 社 |
|
無格社 |
|
|
|
| 鵜羽山社 |
|
無格社 |
|
|
|
| 金比羅社 |
|
無格社 |
|
|
|
| 浅 間 社 |
|
無格社 |
|
|
|
備考ー須賀社以下六社は明治四十二年七月、八幡社に合祀せられて今は
例祭行われず只祠堂を存するのみ。
(1)八 幡 社ー鴨居の鎮守にまします縁起に養和元年六月、源頼朝卿当郡遊覧の
時勧請ありし旨記せり。
(2)亀崎神社ー古は巌窟中に奉祀ありしが今は其所崩れたるを以て石を払ひたる所
に祀る口碑によれば本社は弟橘姫のカメノヲの漂着せしを祭れるなり
二、寺 院
| 山号・寺号・院号 |
境内坪数 |
宗派 |
開基 |
開基年月 |
東光山 西徳寺
量寿院 |
五百四十三坪 |
浄土宗 鎮西派 |
僧 法 誉 |
永禄元年四月 |
| 鴨居山 能満寺 |
四百八十三坪 |
曹洞宗 |
僧 伝 英 |
慶長九年二月 |
| 仏崎山 観音寺 |
|
曹洞宗 太玄派 |
僧 禅 尊 |
慶長六年六月 |
(1)観音寺ー本郡沼間村曹洞宗海宝院の末寺なり。東西十間南北三十七間面積一反三
畝十歩を有す。本尊十一面観音(二尺五寸)を安置す。古より観音堂ありし
を僧霊屋英(寛政八年七月廿九日没)起立して一宇となせしが天正十九年
観音堂料三石の御朱印を下附せられたり。此寺はもと観音崎の最端にあり
て走水の観音と称し遠近の信仰浅からざりしが維新後砲台を改築するに際
し鴨居の亀ヶ崎に移さる。元の寺域は海に臨み岸には岩石崎立し総の山房
の水呼べば応えんとするが如き佳景なりしが現在地亦絶佳の景色にして朝
陽朱欄に映じ白帆崖下を過ぐるの趣あり慶長十七年霊屋が作れる縁起に曰
く。
(前略)十一面観音大士は俗に舟守観音といふ乃ち行基の所造也。住昔此
山に群鵜競ひ集り巨蠎窟に宅り其の害をなすこと鮮からず。方に舟子風を
張り漁者波に駕するの際鵜先づ風来り相尋で蠎穴を出で便ち舟を覆す。是
に由りて運漕漁釣のもの甚だ以て之を患ふ天平十三年春行基東遊して此に
到り乃ち呪して蠎を下す。大士像を手刻して以て窟側に安んず。又別に蠎の
霊を祀り鵜羽山権現と号し以て山の鎮護とす。自爾以来海上安穏に民既に
蠎難を脱す。建保の乱香火を司るの徒蜜に此像を匿し去て其終る所を知らず。
寛元二年夏一小洲の間夜に光あり邑民鳩議し光に就て之を索めしに忽ち此
像儼然たり相倶に驚異し輙奉負而還り殿後の空穴に安置す今猶存す。
(2)能満寺ー東西十八間 南北二十一間 面積一段六畝三歩あり行基作虚空蔵菩薩を安
置す。又寺内に薬師堂あり。薬師の木像二尺五寸行基作を安置す。天正十
九年堂領弐石の御朱印を給はる元来此薬師は多光薬師と称するを土人誤り伝
へて蛸薬師と称し奉納物に必ず蛸の絵を画くを常とす。
(3)西徳寺ー東西二十間 南北二十二間 面積一段八畝三歩あり本県鎌倉郡鎌倉町の字
材木座浄土宗光明寺の末流也。
三、小 学 校
(1)名 称ー浦賀町立尋常鴨居小学校
(2)沿革の大要ー浦賀町立尋常高等鴨居小学校(但高等科は二学年程度)と称せしが明治
四十二年四月小学校令改正の結果浦賀町立尋常鴨居小学校と称し尋常
科六学年までをおく。
四、実業補修学校
五、青 年 会ー浦賀町青年会鴨居支会
六、父 兄 会
浦賀と略同一の目的より成る明治四十三年度に於て二回、同四十四年度に於て四回開会
す現在会員数二百九十九人なり。
七、同 窓 会
(1)現在会員数ー八拾弐人
(2)開会度数ー明治四十三、四年度に於て各一回
第三節 郷土の沿革
一、名 称
古昔より鴨居村と称す。
二、沿革の大要
(1)所 属ー明治元年神奈川府に属し同年十二月神奈川県直轄に帰す。同六年五月第十
五大区三小区に属し同十一年十二月一日三浦郡役所に属し同十七年七月浦
賀宮下町外二拾ヶ町村聯合戸長役場の所属となり後市町村制実施の結果浦
賀町役場の所管となる。
(2)領 主ー上古の事績詳ならず康平六年三浦為通相州衣笠及び沼田の両城を築きて居
住し、同氏の所管に属して子孫に伝はりしが宝治二年三浦氏滅びて北条氏の
有となれり元弘三年北条高時亡びて足利氏に移り永享年間には上杉清方の
所管となれり。永正十五年に北条長氏に転ず天正十八年には徳川氏の所領
となり元禄十三年一たび酒井雅楽頭の領地に転ぜしが享保年間徳川氏に復
す。文化二年には松平肥後守の領地に移り文政十一年には松平大和守領と
なる。嘉永五年細川越中守の預り所となり後慶応二年に至り徳川氏の直轄と
なり以て王政維新の際に至れり。
三、名 勝
(1)観音寺山公園ー明治三十四年四月開園
四、旧 蹟
(1)大筒台場ー今の観音崎砲台なり。昔は山に船見番所をおき大筒五挺を備ふ。傍に陣屋
あり。文化九年平根山に移るゝ一年に造らる領主松平肥後守此頃の陣屋構八
千百十坪余、文政四年浦賀奉行の時となり鉄砲方目付四郎兵ヱに属セリ。
同心二人江戸に来住すること平根山に同じ。
(2)鳥ヶ崎台場趾ー東西七十五間 南北二十五間 面積一千八百七十五坪 文化八年幕命
によりて松平肥後守の建築する所とす。明治元年維新の際廃毀して現今民有
地となる。
(3)亀ヶ崎台場趾ー東西十二間 南北二十間 面積二百四十坪 弘化四年幕命により松平
大和守の建築。明治元年廃毀。
(4)和田義盛の剃髪塚ー鴨居の西徳寺山上にあり。径三間余の松林にかこまる方二間許来
由詳ならず。
(5)石井塚ー小字塚畑にあり。小幡宋海氏の考証によれば是は石井五郎なるものゝ墳墓な
るが如し曰く東鑑に治承四年八月二十四日三浦一党畠山次郎重忠と由井が浜
にて合戦の時、多々羅三郎重春並に郎等石井五郎討死せしこと伝る。推考する
に村内多々羅の小名あり。三郎重春が父四郎義春は三浦大介が四子にして始
めて多々羅と称す。今多々羅の地に土人其居跡を伝へざれども義春此地にあり
て古名を称せしならん。さては此の石井塚といふも郎等五郎の塚なるも知るべか
らずと。
第四節 官 公 署(附重なる建物及設備)
一、尋常鴨居小学校
二、巡査駐在所
三、砲 台
観音崎沿岸北一帯を東京湾要塞地帯とす。
四、燈 台
観音崎に設置しあり。水面より燈火まで十七丈八尺 基礎より燈火まで四丈 第三等の不動
白色にて一千七百五十燭の光度あり光射は北は二十七度、西より南は三十一度、西までは
二百三十八度間にして光達十七海里に及ぶ。此の燈台は横須賀造船所傭仏国技師ウエル
ニーの設計にて起工し明治元年に竣起し明治二年正月元旦より点火を始めたり本邦に於け
る洋式燈台の濫觴とす。
第五節 人情風俗習慣
一、人情風俗
一般に質朴の風ありて概して生業に勤勉なり。
第一編 総 論
第五章 地 勢
第六節 海岸の状態
三、鴨居に接する方は一帯断崖絶壁加ふる暗礁所々に出没して舟行危険なり。北部は奇岩怪
石並立して頗る奇観を呈す。まゝ沙洲あり。
岬=観音崎=突出二町巉岩なり。鳥ヶ崎=突出二町余。亀ヶ崎=突出壱町余。
暗礁=(1)笹根=鴨居の辰の方にあり。東西五十間 南北三十間、面積千五百坪、
干潮の時深さ八尺。
(2)=鴨居の東方にあり。東西二十間、南北三十八間、面積七百六十坪、
干潮の時深さ二尺。
第七章 産 業
第三節 漁 業
鴨居・久比里・走水・浜町の殆ど全部、大津、川間の一部分斯業に従事す。全町の戸数の
六分の一なり。
三、鴨居、走水にては鯛、鰯、鰤等とし鰯は六月より十月まで、漁具は大津と殆ど同一なりとす。
(小手繰網、三双張網、掛網、鮫苗縄等とす)
前同様の調査(明治廿一年十二月の調査)
によれば
漁 船 鴨居 二三〇 走水 二一七
漁 夫 鴨居 三五〇 走水 五七六