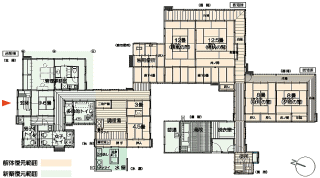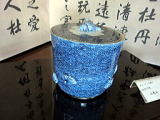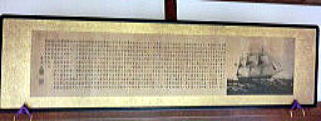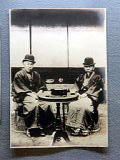明治31年(1898)
大磯の蒼浪閣の庭で、
左が大隈重信
右が伊藤博文
| 園 内 | |||
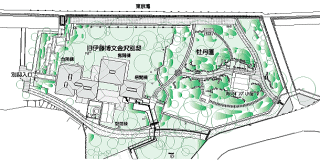 |
|||
| 園内マップ | |||
| 旧伊藤博文金沢別邸は創建当時、客間棟(客間・客用便所)、居間棟(居間・湯殿・便所)、台所棟(玄関・台所・水屋)の3棟で構成されていました。居間棟の湯殿、台所棟の玄関・水屋(新築復元範囲)は、既に壊されて残っていませんでしたが、調査資料を基に復元しました。格式の高い客間棟を海側の最も眺望の良い位置に張り出し、各棟を雁行形に並べ、廊下で繋いでいます | |||
 |
 |
 |
 |
| 台所棟 別邸の玄関で、調理場・水屋などが設けられていました。来客時には、地元の割烹より仕出をとっていたそうです。 | |||
 |
 |
 |
 |
| 客間棟 博文公存命の時から、天皇、皇太子をはじめ、皇族の来邸があり、この客間棟で過ごしたと思われます | |||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 居間棟 日常の生活をする棟です。多忙な博文公にとって安らぎの場所だったのでしょう。 | |||
 |
 |
 |
|
| 水屋 | 湯殿 | ||